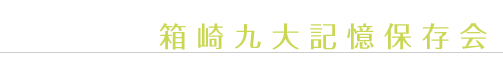昭和45年 文学部入学 A.Sさん
- こんなもの、食べてました。
■■ キャンパスの食堂で
文系キャンパスでは、現在の中講義室の位置に生協食堂があり、文系食堂が今あるところには、書籍部がありました。当時は夕食も出していました、朝食と昼食と夕食。定食ですね。文系食堂は僕の記憶だと16:30頃からだったと思いますが、18:00までやっていました。その頃はコンビニもなければ弁当屋もないし、夕食はほとんどそこで食べていた訳です。夏休みなど、そこ(文食)が休みの時は理学部のところにあった生協の理食という、理学部の食堂があったんです。
工学部食堂内部
■■ 食事も、時間との戦い
時間というものが限られていました。今はすべてが24時間の時代ですけども、食堂にしても何にしても、時間や時期が限られていました。お盆や年末年始などのほか、何時に始まるだとか。食堂だとか買い物をするところが空いている時間、閉まる時間がハッキリしていました。とにかく何時までに帰らないとそこの店が閉まっているとか、風呂は何時までとか。…文学部の人は18時までに夕食を食べなければならなかったわけです。ところが18時を過ぎても開いてるところがあった、工食です。地下だったと思うんですけどね。業者が入っていました。工食は19時頃まで開いてた。生協は当時は定食しかなくて、工食は好きなおかずを取ったりして食べられました。生協は日曜日は休みで中央食堂だけ開いていて、あとはその辺の食堂に行っていました。自炊をやる場所もなかったし、ほとんど外食でしたよ。
■■ カップラーメン
カップラーメンができたことは画期的でした。で、カップラーメンが出来た当時、自動販売機でカップラーメンがでて、お湯が出るのがありました、今はあるのか分からないですけど、あれはね、画期的でしたね。だからね、学生さんが暗い中、自動販売機の前で3分間待っている、そういう光景がありましたね。
- その生活ぶりは……
■■ 下宿・間借り
夜にご飯を出すいわゆる下宿はあったけど、ちょうど僕の時期には少なくなっていました。段々とアパートが増えていった時代。…(間借りをしていた)僕のところはお風呂場もなかったし、井戸水が、古い家の一階の真ん中のところに、庭でもないんだけど土間があって、そこの井戸水で洗濯をしていました。
■■ 入浴は、何時から?
前はお昼、少なくとも2時頃には(銭湯が)開いていたのではないでしょうか。学生さんは時間があるから、お昼開いたら、2時位から行くわけです。そしたらそこにいるのはおじいさんと学生しかいない(笑)。そんな時間にお風呂は入れるのは。で、おじいさん達は一時間ぐらい、学生はちゃかちゃかっと入って出ていました。僕らは恵比寿湯に行っていて、恵比寿湯の斜め前に赤のれんていうラーメン屋がありました。…恵比寿湯で風呂にはいって、その後赤のれんで食べて帰ってくるという、そういうことをやっていました。…近くの銭湯が休みのときは、遠くに行きます、遠くというのは新楽湯だとか大学湯ですね。
- こんな人たち・物たちにお世話になりました。
■■ いざ、洗濯!
いっしょの家にいた法学部の一級上の先輩から、小さな洗濯板を譲り受けて、それで洗濯をやっていました。丁度そのころはコインランドリーが出てきた頃。僕は使わなかったけど、研究室の先輩が、箱崎の割と広い家に結婚して住んでいました。新婚生活で洗濯機があり、そこにいつも洗濯物を持って行っていました。今では本当に迷惑をかけていたと思うんだけど(笑)、今でも奥さんには頭が上がりません(笑)。洗濯を待ちながらビールを飲ませてもらうだとか、そういうことがよくありました。
■■ 公衆電話
角のタバコ屋にはポストがあって公衆電話があると。ともえ食堂からちょっと行った、ふなこしの所ですね、ふなこしさんの曲がるところの角のところにあったと思います、タバコ屋さんが。おばあちゃんが座っていて、そこに公衆電話があって、市外にかける時はおばあちゃんが鍵を開けて、普通(の市内)電話は10円だったから、鍵を開けてくれて、そして交換をしてもらって、大分なら大分の何番って言って(取り次いでもらい)、その後終わったら「2通話でいくらでした」って言われて、お金を払うわけですね。
そういう電話をかけるにしても、公衆電話はあったんだけども、市外にかけたりするにはそういうコミュニケーションが必要だったわけです。誰かにお世話にならないとかけられない。で、その後コインだけで市外電話をかけられるような電話になっていったんですけど、以前は市内電話だけしかコインでかけられませんでしたね。…そういう公衆電話の場所も、当時としては非常に大きかったですね。
■■ 研究室(光熱費的な意味で)
研究室が生活の場でした。僕らの頃は10時まで研究室にいて、で10時になると二人の警務員さんが研究室をずーっとまわって、『10時になったから帰りなさい』と追い出されるわけです。で、全部研究室の火元が大丈夫か見て、今は(見回りが)ないですから危ないですよね。…夜10時までは学校で勉強できたわけです。少なくとも水やお茶はあるし、それから当時は灯油のストーブがありましたら、光熱費がいらないわけですね。クーラーなんかはないけど、扇風機はありました。
- あの頃の娯楽
■■ コンパ

三畏閣正面
■■ 貸本屋
恵比寿湯の向かいに貸本屋さんがありました。結構ね、昔は貸本屋さんというのがあって、雑誌でも漫画でも何でもね、借りてね。それから食堂には漫画とか雑誌とか結構ありました。だから食べるときに何していたかと言うと、その頃からよく言われたのは、学生が昔はお喋りをしながら食べてたのが、今は一人で漫画を読みながら食べるという、そういう風によく言われたもんですよね。
■■ 飲み屋
箱崎は昔は飲み屋でも何となく棲み分けがなされていたような気がします。学生さんを中心とした所と社会人を中心とした所と。割と箱崎は職員の人とか一般の人たちが行く飲み屋と、学生さんが行く飲み屋と(分かれていました)。…僕らがほとんど行かないところがあった、値段の問題もあるし、逆に学生ばかりのところに社会人も余り来なかったですね。
■■ 映画館
映画館は箱崎に三つ位(?)はありました。箱崎東映というのが網屋町四ツ角からすぐの所に。…箱崎東映はその昔は畳敷きだったようだが、僕らの頃にはもう畳ではなくなっていました。
- 思いでのお店
海門
・昔は電車道沿いにあった(今は移転しています)・70年代初め、サントリービールが出はじめた頃、サントリーしかおいていなかった(出始めであまりおいしくなかった)。向かいの店はキリンビールだった。しかし海門には刺身を置いていたので、少しお金に余裕がある時は、サントリービールでも我慢した。
・カウンター以外、テーブルが一つか二つ位の広さだった。
・夫婦でやっていた。その後の新しいお店でもおやじさんがいて、昔話をよくしたものだ。
かよ食堂(通称:かよちゃん)
・海門(移転する前の電車道沿い)の斜め前にあったお好み焼き屋。学生の客が多かった。・4人姉妹の2番目のかよちゃんがお店を切り盛りしていた(4姉妹のお母さんが当時配膳をしていた)。
・鉄板のまわりにカウンターがあり、テーブルもいくつかあった。焼きそば、焼き魚、冷奴や枝豆はじめ、定食から何から色々なものを出していた。
・店の奥が座敷になっており、10〜15人ほど入れるため、コンパ会場になっていた。
・80年代に閉店。
箱崎松原郵便局周辺
・グリル(カレー専門店): 太ったおじさんがマスター、進駐軍で賄いをやっていた(らしい)。学生には少し高く、先輩がアルバイトの給料が入ったときに連れて行ってもらったりしていた。・おたふく: むかしながらの食堂で、お兄さんが(当時20、30代)出前をしていた。入ったことはほとんどなかったが。
赤のれん
網屋立筋、恵比寿湯の斜め前にあった。屋台から出発したお店。ラーメンがうまくて有名だったが、当時は箱崎では珍しいファミレス風中華料理屋だった。恵比寿湯の風呂上がりに、赤のれんでビールとラーメンという時もあった。新楽通り
・左右に色んなお店があったが、近年の道路拡張工事で片側だけが残った。・平松屋のてんぷら定食(松・竹・梅)はなつかしい。夫婦でやっていた。
・梁山泊 筥松郵便局前、おいしい餃子屋で、九大の人で知らない人はいない位だった。目の前に大きな鉄板があり、夫婦でやっていた。割と小さめの餃子で、皮からおじさんがひとつづつ目の前でつくる。一回で40個ほどは軽く平らげていた。
・酒屋の上滝は今でも昔のまま残っている。